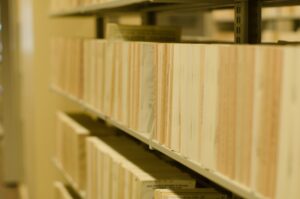改正相続法による遺言書の書き方:相続人関係で遺言書を残すべき3つの代表的ケース
遺言書は、あなたの想いを未来へと繋ぐ大切な手段です。特に相続においては、遺産分割を円滑に進め、相続人間の争いを避けるために、遺言書の作成が非常に重要となります。改正相続法を踏まえ、どのような場合に遺言書を作成すべきか、具体的なケースを3つご紹介します。
【第1位】お子様のいらっしゃらないご夫婦
お子様のいないご夫婦の場合、相続は複雑になりがちです。特に、以下の2つのケースでは遺言書が不可欠と言えるでしょう。
(1) 配偶者のご両親がご存命の場合
改正相続法では、配偶者のご両親にも遺留分(遺産の一定割合を相続できる権利)が認められています。そのため、ご両親がご存命の場合、遺産分割協議において、ご両親の意向を無視することはできません。
もし、配偶者の方に多くの財産を相続させたいのであれば、「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成しておくべきです。これにより、遺留分を侵害しない範囲で、配偶者の方に最大限の財産を相続させることが可能になります。
殊に、嫁と姑の関係等で義理の親との関係が微妙な時は遺言が不可欠です。
(2) 配偶者のご兄弟姉妹がいらっしゃる場合
配偶者のご兄弟姉妹には遺留分はありません。しかし、法定相続人となるため、遺産分割協議に参加する必要があります。
もし、配偶者の方に全ての財産を相続させたいのであれば、「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成しておくべきです。これにより、ご兄弟姉妹の権利主張を排除し、配偶者の方にスムーズに財産を承継させることができます。
参考:民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
【第2位】法定相続人がいない方
「自分には相続人がいない」と思い込んでいるケースは少なくありません。しかし、実際には、疎遠になっている親族が法定相続人となる可能性もあります。
無料法律相談であっても、相続に詳しくない専門家の場合、安易な判断をしてしまうことがあるため注意が必要です。
大学教授が講義で「笑う相続人」の話をされた事例もあるように、長年音信不通だった親族が、思いがけず相続権を主張してくるケースは少なくありません。
このような事態を避けるためにも、遺言書の作成は有効です。遺言書があれば、遺産の分配方法を自由に決めることができ、予期せぬ親族の出現によるトラブルを回避できます。
なお、相続人がいない場合、遺産は最終的に国のものとなります。もし、特定の団体や個人に遺贈したいという希望があるのであれば、遺言書にその旨を明記しておく必要があります。
相続おもいやり相談室では、寄付を勧めています。寄付は元来善意に基づくものなので、その気持ちを大切にしたいと考えています。
【第3位】相続トラブルが予想される場合
相続人の中に、認知症の方や、海外在住で連絡が取りにくい方がいる場合、遺産分割協議が難航することが予想されます。
(1) 事理弁識能力の低い相続人がいる場合
アルツハイマー等の病気で事理弁識能力が低い相続人がいる場合、遺産分割協議に参加することができません。そのため、成年後見人を選任する必要がありますが、手続きに時間と手間がかかります。
遺言書があれば、遺留分を考慮すれば、遺言内容に沿ってスムーズに遺産分割を進めることができます。
(2) 海外に居住している相続人がいる場合
海外に居住している相続人がいる場合、連絡や手続きが煩雑になることがあります。特に、相手国の制度や言語の問題で、スムーズに連絡が取れないケースも少なくありません。
遺言書があれば、遺産分割協議をせずに、遺言内容に沿って遺産分割を進めることができます。
(3) 相続財産に強い執着がある相続人がいる場合
相続人の中に、被相続人の財産に強い執着がある方がいる場合、遺産分割協議が紛糾する可能性があります。
遺言書があれば、被相続人の意思を明確に伝えることができ、相続人間の感情的な対立を避けることができます。
相続おもいやり相談室では、弁護士との連携により、紛争解決をサポートしています。
3人以上の相続人がいる場合は遺言書が有効
3人以上の対等な立場の相続人がいる場合、遺産分割協議は複雑化しがちです。それぞれの相続人が異なる思惑を持っているため、合意形成が難しくなることがあります。
また、高齢化社会の進展により、相続人の数が増える傾向にあります。親族関係が希薄になっている現代社会においては、遺言書によって、被相続人の意思を明確にしておくことが重要です。
離婚や再婚によって、前婚の子と後婚の子がいる場合も、相続問題が複雑化する可能性があります。遺言書によって、誰に何を相続させるかを明確にしておくことで、将来の紛争を予防することができます。
永い人生でお世話になった人や法人に遺贈したい場合も、遺言書にその旨を記載しておくことで、他の相続人とのトラブルを避けることができます。
事業承継には遺言書が不可欠
個人事業の場合、経営者が亡くなると預金口座が凍結され、事業運営に支障をきたす可能性があります。遺言書があれば、後継者へのスムーズな事業承継が可能になります。
株式会社の場合、株式を後継者に集中させることで、経営権の分散を防ぎ、円滑な事業承継を実現することができます。
遺言書は、あなたの想いを未来へと繋ぐ大切な手段です。相続に関するお悩みは、相続おもいやり相談室までお気軽にご相談ください。